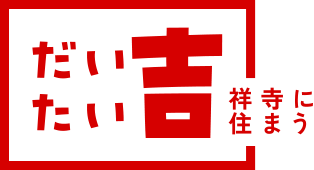手抜き料理をするぞ、という固い決意のもと、スーパーでパスタソースの棚を眺める。
さまざまな種類が並んでいるが、私は「青の洞窟」シリーズが好きだ。本日は無難にボロネーゼを選ぶ。
ところが帰宅して台所に立つと、フライパンをガスコンロに載せている。冷蔵庫にしなびかけのトマトとナスがあるのを発見したので、それを使ってパスタソースに一手間加えることしたのだ。
鍋で湯を沸かしているあいだに、フライパンにオリーブオイルをちょっと入れ、トマトとナスを炒める。コショウを振り、ボロネーゼのパスタソースを投入。トマトの水分で味が薄くなってしまうかなと思い、ピザ用のチーズも入れる。チーズがとろりと溶けて、おいしそうなナスのボロネーゼになった。嵩が増えたので、パスタも心持ち多めに茹でようっと。
手抜きは手抜きだが、私が意図していたのは、こういう料理ではない。茹でたパスタに、チンしたパスタソースをかけて、はいできあがり、って段取りを目指していたはずなのに。なぜ、トマトやナスを切ったり、フライパンを使ったりしているんだ。
答え:食いしん坊だから。一手間加えると、具だくさんのパスタが食べられるから。
むろん、パスタソースの底力があってこそで、ありがたいことなのだが、調理をするなら、もういっそのこと一からボロネーゼを作っても同じだったのではないか、と思わなくもない。せめて洗い物は減らしたいと思い、パスタはフライパンから直接食べる。おしゃれさが微塵もない。
この行い、私の人生を象徴しているような気がする。中途半端になにかが過剰なのだ。
たとえばエッセイや小説を書くと、原稿がそのままみなさまの目に触れるのではなく、あいだに「ゲラ」という作業が挟まれる。「校正刷り」が送られてきて、そこで一、二回ぐらい、文章や体裁をチェックするのである。校正者のかたが確認し、「ここは事実と異なるのでは?」と指摘をしてくれることもある。それについても検討し、修正するかどうかを判断する。
このゲラの作業も、手抜きをしたいとはまったく思わないが、毎回、「タイムリミットも迫っているし、ほどほどの確認にしよう」と自分に言い聞かせる。ところが毎回、気づくと目を皿のようにして、自分の書いた文章を鬼のごとくチェックしまくっているのである。編集者のかたが、「もうそのぐらいでいいんで、早くゲラの作業を終わらせてください」とあきれるほど、血眼。
どんだけ自分の文章が好きなんだよ、と思われるかもしれないが、逆で、「絶対にまちがいや、洗練されていない文章があるはず」と自分への疑心暗鬼が発動し、睡眠時間を削ってゲラをやってしまうのだ。原稿段階から完璧な文章を書いておけばいいのに⋯⋯。追いこまれてから、本気を出す。中途半端になにかが過剰。
パスタソースにいちいち一手間かけてしまうのも、どこか同じ心性が働いているのではと思える。私の原稿とちがって、パスタソースはすでに充分においしいのに、さらに「もうちょっとなにかを添えてみよう」と、いらぬ工夫を施してしまう。結果としてパスタソースの分量が増え、パスタの量も増える。
すなわち、太る。
先日、私は雑誌のインタビュー依頼があり、写真を⋯[続きを読む]
著者:三浦しをん(みうら・しをん)氏
1976年、東京生まれ。
2000年『格闘する者に○(まる)』でデビュー。
2006年『まほろ駅前多田便利軒』で直木賞、2012年『舟を編む』で本屋大賞、2015年『あの家に暮らす四人の女』で織田作之助賞、2018年『ののはな通信』で島清恋愛文学賞、2019年に河合隼雄物語賞、2019年『愛なき世界』で日本植物学会賞特別賞を受賞。
そのほかの小説に『風が強く吹いている』『光』『神去なあなあ日常』『天国旅行』『墨のゆらめき』『ゆびさきに魔法』など、エッセイ集に『乙女なげやり』『しんがりで寝ています』『好きになってしまいました。』など、多数の著書がある。

撮影 松蔭浩之