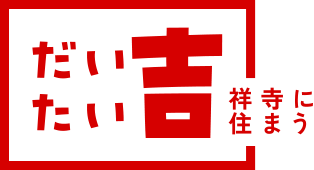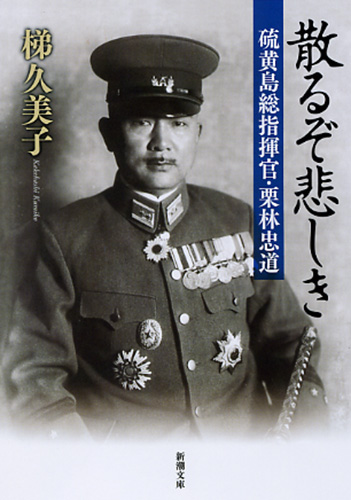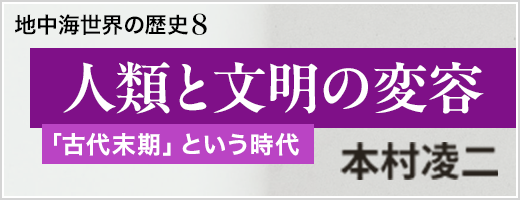戦後80年の今年、国内に生まれてから一度も戦争を体験したことない人は9割になったそうだ。それは、とても幸せなことなのは確かだ。一方その間にも他国では戦争や紛争は続いており、多くの人々が命を落とし、家族を亡くし、生活を粉々にされている。
そして戦後80年の今でも広島や長崎など戦争による大きな傷跡は、日本国内にも数多く残っている。年齢を重ねながら、他国の状況を垣間見、歴史を更に知ると、平和を維持することは決して簡単なことではないのだと実感できるようになってきた。
『散るぞ悲しき 硫黄島総指揮官・栗林忠道』を何年かぶりに読み返してみると、初めに読んだ時よりも更に胸に迫るものがあった。職業として軍人の道を歩む栗林はアメリカに留学した経験もあり、国力の差を肌で感じた彼には、この戦争に勝ち目がないこともわかっていた。しかし国を守り、戦うことを退けるわけにはいかない。指揮官としてのバランス感覚や明晰さの一方で、家族に対する細やかな愛情も併せ持つ栗林指揮官。妻や子供達への気配りのある手紙から、どれだけ愛情深い夫や父だったのか伝わってくる。
彼を敬愛する部下の記録や、怖れる米軍の反応などから、硫黄島での戦いがどれだけ無謀でかつ日本にとっても重要だったかを、この著作で知った。そして硫黄島で戦い、骨となっても家族のもとに戻れないまま、島の地中に埋まっている数多くの軍人たちを思うと、それぞれに大切な人がいて、また逢える時を楽しみにしたり、大切な人の未来のために命を差し出さざるを得ない状況になっていく無念さが身に沁みた。
本作はノンフィクション作家・梯久美子さんの作家としての一作目であり、2006年の大宅壮一ノンフィクション賞を受賞した作品である。こんな骨格のしっかりした、そして細やかな作品を20年も前に刊行したのかと思うと、傑作という言葉しか出てこない。そして、戦争とは人間にとってどのようなものなのか、読む度にはっきりと心に刻まれる大切な作品だ。読んだあとに「良い戦争なんてない」とまた思ったのだった。
戦場に行かないだろう政治家にも、必ず読んで欲しい。
2025.9.15(M)