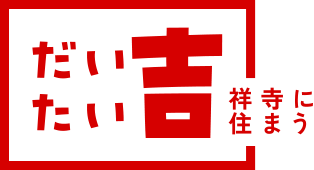毎年人間ドックの検査も行い、人一倍健康に気を付けている夫が、突然に体調を崩し入院。3ヶ月も病名を診断されないまま弱っていって、それでもどうやらがんのようだとわかった時の著者の驚きと悲しみ、動揺はどれだけのことだっただろうか。あのコロナ禍で、面会もなかなか自由にできないまま、食事もさせられない状態で鼻からのチューブでコントロールしながら、そして検査しても病気が何だかわからない状況が3ヶ月って、患者さんだって絶望しそうだし、著者の東さんの気持ちは、想像できるとはとても言えない。そして見つかったのが、「原発不明がん」という聞き慣れないがんだった。
がんの大元の病巣がどこにあるのかわからない希少ながんを、原発不明というらしい。そのがんがどこから始まったのかによって、がんの治療方針は変わってくるそうで、原発不明は厄介だし、治療方針が判明するまでに時間もかかるようだ。東さんの夫がこのがんだとわかった時には、もうすでに残された時間がほとんどないと言えるくらいに体は弱り切っていて、そこから抗がん剤治療が始まるが、それも短い期間で中止となる。
そして最終的にはご自宅での緩和ケアを選択し、退院後に18日間自宅で穏やかな日を過ごして、他界されてしまう。
夫の体が弱っていく中で、著者の気持ちの混乱や、信頼しきれない病院からの転院、転院先での手厚い医療や看護などが、静かで読みやすい文体で経過していくのだが、これは本当に耐えられないだろうなという出来事が次々に起こっていく。そして著者のいたたまれない気持ちが、読む側の自分にもダイレクトに伝わってきた。
これは特別な出来事ではなく、自分にも起こりうる出来事なのだ。
本書では、著者の惑いを解き明かすようになるべく情報を整理して読者に提示し、一家族の闘病記にとどまらず、誰にでも起こるかもしれない希少がんをわかりやすく説明してくれている。そして現在の医療体制や介護にまつわることなども細かく記してある。医師をはじめ、関わった医療関係の人々へのインタビューも的確で、凄みさえ感じてしまう。
パートナーを失った喪失感に、他に何かできなかったかの後悔の感情、現在の心境などいわゆる病気と向き合った家族の闘病記でもある一方で、それ以上に自分が知らなかった「原発不明がん」との向き合い方を多くの人たちに読んで欲しいという思いが溢れている著作であった。頭が下がるばかりである。
2025.12.14(M)