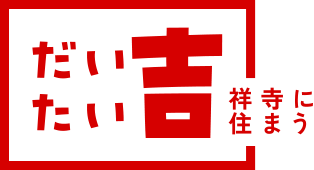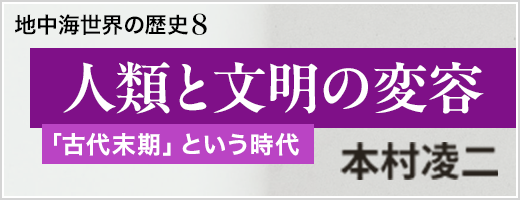あまりの暑さ続きに筆が進まない原稿を、それでもまとめつつあったときに、裏千家15代家元でいらした千玄室さんがご逝去なさった報道を知りました。享年102歳。太平洋アジア戦争の後、一貫した姿勢で、日本国内のみならず世界各地で「茶の湯外交」を展開なさって、静かに平和の尊さを説き続けられ、日本の文化勲章のみならず、多くの国から感謝され、表彰された方だということは有名ですし、新聞やテレビの報道でも繰り返されていました。
現役時代の私が、学習院大学で管理職にあって多忙な日々を送っていた頃に、何年の何の折にであったか、改めて昔の手帳を引っ張りだしてページをめくらないとそれは定かではないのですが、大学にいらしてくださったことがあり、直接お目にかかって少しの時間ながらお話をさせていただく機会がありました。そのくらいの役得がなければ、管理職などやってはいられないので、貴重な機会が持てるチャンスは、万難を排して生かさせてもらっていたものです。
背筋のシャンと通った姿勢で凛とした雰囲気をただよわせておられた玄室さんは、何の話題の流れであったか、記憶は定かではありませんが、学徒出陣で海軍へ入隊し、特攻隊の基地で同年代の仲間が隊員として先に出陣して飛び立って行くのを、複雑な思いで見送っていたのだということを、静かにお話しくださいました。これは、私の推察ですが、当時の方としては背が大変高かった玄室さんは、それゆえに出陣の順がうしろになっていたのではないか、とも思えます。今回の報道の中には、海軍や特攻隊を志願したという紹介もありましたが、これは学徒出陣で召集され入隊せざるをえなかった当時のあり方を、あまりにも知らなさすぎるか省略しすぎの単純な説明にすぎるように思います。
私の学生時代の指導教授であった柴田三千雄先生は、勤労動員中に学徒出陣の徴兵令が来て、千葉は習志野の師団に出向いて間もなく終戦となり、前線に出ずに済んだが、千葉の部隊でも本土防衛のためにといって、特攻隊の訓練がなされていたという話を、してくださったことがありました。
また、私が一時期教鞭をとらせてもらっていた東京経済大学でも、戦後に自由民権運動史の研究をリードなさったことで有名な色川大吉先生がいらして、いろいろな対話をさせていただいた折に、色川先生もまた、学徒動員で行かざるをえなかった特攻隊の基地で、終戦を迎えたのだという話をうかがい、どの時代にどの人生の時期を生きるかという偶然が、その人の思想や立場を超えて運命を決定づけるという、無慈悲な現実を考えさせられたものです。
特攻隊の訓練を受けていた基地で、仲間と屈託のない笑顔で写真におさまっておられる千玄室さんの姿も、新聞などで紹介されていましたが、これをあたかも進んで特攻隊に志願したという話とかぶせてとらえるのも、いかがなものかと私には思えます。若い彼らが皆でそろって、家族に送られるかもしれない写真に笑顔でおさまっていたからといって、それをもって、進んで志願して、敵艦船につっこめる片道の燃料しか積んでいない攻撃機に乗って出た、というほど若い彼らが単純な心情の持ち主であったとは、それこそ複雑な人間心理をふまえていない単純な捉え方にすぎると、私には思えます。
千玄室さんは、戦後、ご自分が世界各地で茶道を広めながら、平和の尊さを説く活動を続けるうえで、そのような、たしか「無念な」という言葉を使われたように記憶に残っているのですが、戦時体験が大きかった、というお話でありました。そうしたご経験をまったく存じ上げなかった当時の私は、お話に驚くとともに、あらためて、これからを担う若者である学生たちを教育するという自分の立ち位置に、襟を正したことを、よく憶えています。
私自身は、憲の字を用いた名前から想像されるかもしれませんが⋯[続きを読む]
著者:福井憲彦(ふくい・のりひこ)氏
学習院大学名誉教授 公益財団法人日仏会館名誉理事長
1946年、東京生まれ。
専門は、フランスを中心とした西洋近現代史。
著作に『ヨーロッパ近代の社会史ー工業化と国民形成』『歴史学入門』『興亡の世界史13 近代ヨーロッパの覇権』『近代ヨーロッパ史―世界を変えた19世紀』『教養としての「フランス史」の読み方』『物語 パリの歴史』ほか編著書や訳書など多数。