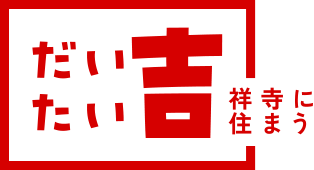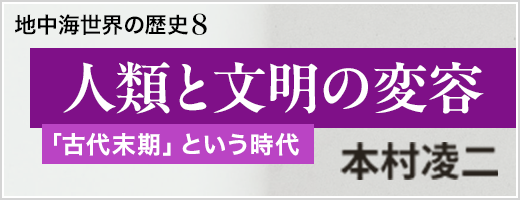私自身は、憲の字を用いた名前から想像されるかもしれませんが、1946年11月の生まれです。この年に新憲法が制定されたことに由来する命名です。
現行の日本国憲法は、GHQ(連合国軍総司令部)の監督下であれ、はじめ幣原喜重郎内閣のもとで1946年3月に、主権在民や象徴天皇制、戦争放棄を含む「改正草案要綱」として発表され、その後、5月に成立した第一次吉田茂内閣のもとで、8月から10月にかけての衆議院と貴族院での審議と修正を経て可決され、1946年10月7日に成立しました。参議院でなく貴族院?と思われるかも知れませんが、GHQ監督下でも敗戦後すぐには、旧体制の議会から戦犯として排除された議員を除外した状態で、議会体制が再出発していたのでした。こうして可決成立した新憲法が、11月3日に公布されます。5月3日が「憲法記念日」なのは、公布半年後の1947年5月3日が、新憲法の施行開始の日だからです。11月3日は明治期の旧暦では9月22日で、明治天皇誕生日(天長節)でしたが、偶然の一致なのか、あえてそれに合わせたのか、それは専門家ではない私にはよく分かりません。いま11月3日は「文化の日」で休日ですが、これが制定されたのは1948年7月の「国民の祝日法」によるものですから、新憲法制定の2年後でした。
いずれにしても、この時期に生まれた戦後ベビーブーマーの先駆けの子には、憲法の憲の字や、平和の和の字が与えられている場合が少なくないのは、この時期を生きた人たちの心を映しているように思います。
幼児期の記憶は、いったい何歳ごろからのものが残るのだろうか、ということは、私にもよくわかっていませんが、今回は本題に入る前に、私が敬服していた千玄室さんご逝去の報が入ったことで、記憶の戦後は次回に書かせてもらおうかと思います。
まだ戦災の跡が残り、高いビルも皆無であった戦後しばらくののち、当時私の家族が暮らしていた代々木の少し高くなったところからは、隅田川の花火が遠く小さく見えたおぼろな記憶が残っていることだけ書いておきましょう。それが、私が何歳の頃であったかは定かではありませんが、私は7歳を迎えた年の翌春に、その当時まだ木造2階建ての校舎であった武蔵野市立第一小学校2年生に転入しましたので、花火の記憶が1953年以前であることだけは確かでしょう。

著者:福井憲彦(ふくい・のりひこ)氏
学習院大学名誉教授 公益財団法人日仏会館名誉理事長
1946年、東京生まれ。
専門は、フランスを中心とした西洋近現代史。
著作に『ヨーロッパ近代の社会史ー工業化と国民形成』『歴史学入門』『興亡の世界史13 近代ヨーロッパの覇権』『近代ヨーロッパ史―世界を変えた19世紀』『教養としての「フランス史」の読み方』『物語 パリの歴史』ほか編著書や訳書など多数。