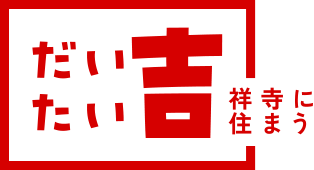山谷町とはよく名付けたものだと思うのですが、北に位置する新宿にかけては比較的平坦でしたが、南側では子どもには崖みたいに感じられる地形で、下に通っている、代々木駅からの道路と小さな川を隔てて、その先はまた高くなっていて、そこから南は大きな明治神宮の境内が広がっています。神宮内苑への正面入り口にあたる南門、つまり原宿側とは逆の側になりますが、まさに山谷町側に西門があり、そこから甲州街道に向けて西参道がのびています。いまでは首都高が、神宮北端にそって西参道沿いには高架で走っていますから、現代化というのはつまらん街を作ってしまう一例か、と。小田急の参宮橋駅とは、この明治神宮に西門から参宮するための橋の名に由来する名前で、このあたりから小田急線は、傾斜地の下側になるという位置関係です。
私は、ここに暮らしていた幼少期、じつは幼稚園を脱走して、嫌だもう行きたくない、とガンとして通園拒否をしたのでした。何が嫌だったのかは、よく覚えていないのですが、困惑した母親が説得しようにも、まったく受け付けなかったそうです。まあ頑固ちゃんだったのですね。当時は遊ぶところといっても子供用にあるわけでなし、空き地にときどき回ってくる紙芝居屋さんが、近所の子供達の絶好の楽しみでしたので、たまたま気づいた時には見に行ったものですが、そこで売られている駄菓子類は、お金も持たせてはもらっていませんから、ほとんど楽しむことはできなかった記憶です。でも時々食べた爆弾あられというのが、ようするにポップコーンみたいなものでしたが、妙に記憶に残っています。
幼稚園中退の私は、すぐ近くに住んでいた同い年くらいの男の子などと一緒に、参宮橋を越えて左側にある東京乗馬クラブの外から、馬場を走る馬の姿に見惚れたりもしましたが、さらに進んで神宮の西門から入って、しばらく進むと広がっている宝物殿前の芝生の広場で駆け回って遊んだり、その前にある池でお玉じゃくしを捕まえたり、バシャバシャ水をかけあったりと、いわばとっておきの、子どもにとっては広大な遊び場として使わせてもらっていました。池の先には空襲で焼失した本殿とそのまわりの森がありましたが、そこまで潜り込んでみるほどまだ大きくはなかったといいますか。宝物殿一帯は、空襲からは免れていたのです。その近くの森のあたりまでは覗きに行ったりはしていた記憶がありますから、私が緑の木々の空間がいかに重要かということにこだわるようになった原点は、この時の経験が少なからず作用しているのかもしれません。
* * *
幼稚園は中退しましたが、山谷教会という、私の母親が戦後代々木に転居した後にクリスチャンとしての洗礼を受けたプロテスタント教会には子供向けの日曜学校があり、そこには通っていました。その教会の、当時はまだ比較的若かった女性の牧師さんであった野呂先生は、実は私が1年生として通うようになった山谷小学校のクラスの担任でもありました。私は1年生までしか山谷小学校にはいませんでしたが、とても元気の良い、子どもたちを惹きつける力のあった野呂先生は、牧師さんでもあったからでしょう、近くの広大なワシントンハイツにある教会や、そこに住むアメリカ人家族の子供達との交流に、私を含む何人かの日本の子供たちを連れて、何度か訪問しに行ったものでした。ワシントンハイツというのは、明治神宮に隣接して、日本陸軍の練兵場としてあった広大な敷地を、敗戦後、連合国軍のうちの駐留米軍、特に空軍の将校とその家族が中心に暮らす住宅地として開発した特別居住区で、衣食住に不自由であった外の日本市民の暮らしとは全く別に、学校やら運動場、教会、各種店舗やクラブハウスなど、アメリカ流市民生活が可能なように、整えられたものでした。私ら子供の目にも、その違いがあまりに強烈であったことが記憶に残っています。
このワシントンハイツは、1964年の東京オリンピックの選手村を設置するために返還され、そのあと一部がオリンピック記念青少年総合センターという立派な施設の場となり、代々木公園や各種運動施設、そして内幸町にあったNHKが放送センターとして移転したのでした。現在の姿のもとが成立したわけです。そのワシントンハイツの名前が、先のジャニーズ事務所の一大スキャンダルのおおもとであった故ジャニー喜多川がそもそも将来性ある少年や児童に接触し始めた場所として出てきたのには、またビックリ。子供野球の指導などしてアプローチしはじめたというような話もでていたようで、いやはやな世の中だと。世の中の光と闇とは背中合わせなのかもしれません。

明治神宮 宝物殿前芝地(PIXTA)
著者:福井憲彦(ふくい・のりひこ)氏
学習院大学名誉教授 公益財団法人日仏会館名誉理事長
1946年、東京生まれ。
専門は、フランスを中心とした西洋近現代史。
著作に『ヨーロッパ近代の社会史ー工業化と国民形成』『歴史学入門』『興亡の世界史13 近代ヨーロッパの覇権』『近代ヨーロッパ史―世界を変えた19世紀』『教養としての「フランス史」の読み方』『物語 パリの歴史』ほか編著書や訳書など多数。